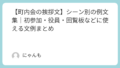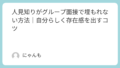手紙やビジネス文書の冒頭でよく用いられる「時候の挨拶」。
相手に季節感を伝えるとともに、礼儀を尽くした丁寧な印象を与える効果があります。
しかし、
❓「どの時候の挨拶をどの月に使えばよいのか」
❓「春と秋のどちらで使える表現なのか」
迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、春夏秋冬それぞれの季節にふさわしい挨拶を、月別に整理した例文集としてご紹介します。
すぐに使える定番表現から、やや改まったビジネス向けの挨拶まで網羅しました。
時候の挨拶とは?基本と使い方
時候の挨拶の役割
例文
- 「拝啓 新春の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。」
使用シーン
ポイント:ビジネスメールの日常連絡では、長い時候の挨拶は不要。「お世話になっております」に軽い季節の一言を添える程度で十分です。
ビジネスとプライベートの使い分けポイント
相手との関係性や場面に応じた言葉選びが大切です。
ビジネスでは形式を重視し、プライベートでは親しみのある表現を選びましょう。
参考記事:【1月〜12月対応】月別ビジネス挨拶文の例文と使い分けポイント
冬の時候の挨拶(12月〜2月)
12月(師走)
意味・ニュアンス:年末の慌ただしさ・寒さの深まり
例文
- 拝啓 初冬の候、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
- 師走の候、年末ご多忙の折、いかがお過ごしでしょうか。
1月(睦月)
意味・ニュアンス:新年の始まり・寒さのピーク
例文
- 拝啓 厳寒の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。
- 新春の候、旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
2月(如月)
意味・ニュアンス:冬の終わり・春の兆しが感じられる頃
例文
- 拝啓 余寒の候、皆様ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
- 立春の候、なお寒さ厳しき折、いかがお過ごしでしょうか。
春の時候の挨拶(3月〜5月)
3月(弥生)
意味・ニュアンス:春の始まり・寒さが残る時期
例文
- 拝啓 早春の候、皆様におかれましては益々ご健勝のことと存じます。
- 春寒の候、寒暖差の厳しい折、ご自愛くださいませ。
4月(卯月)
意味・ニュアンス:春の盛り・暖かく華やかな季節
例文
- 拝啓 陽春の候、皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げます。
- 花冷えの候、桜も見頃を迎えましたが、いかがお過ごしでしょうか。
5月(皐月)
意味・ニュアンス:初夏に向かう爽やかな季節感
例文
- 拝啓 新緑の候、貴社ますますご隆盛のことと拝察いたします。
- 薫風の候、さわやかな季節となりました。皆様におかれましてはご健勝のことと存じます。
夏の時候の挨拶(6月〜8月)
6月(水無月)
意味・ニュアンス:夏の始まり・梅雨入りの時期
例文
- 拝啓 向暑の候、皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
- 入梅の候、湿気の多い日が続きますが、体調など崩されておりませんでしょうか。
7月(文月)
意味・ニュアンス:暑さのピーク・真夏の季節感
例文
- 拝啓 盛夏の候、貴社ますますご繁栄のことと存じます。
- 炎暑の候、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
8月(葉月)
意味・ニュアンス:夏の終わり・残暑の時期
例文
- 拝啓 晩夏の候、皆様におかれましては益々ご清栄のことと拝察いたします。
- 残暑の候、暑さ厳しき折、どうかご自愛ください。
秋の時候の挨拶(9月〜11月)
9月(長月)
意味・ニュアンス:秋の始まり・涼しさを感じる時期
例文
- 拝啓 初秋の候、皆様にはご清祥のこととお喜び申し上げます。
- 秋涼の候、いかがお過ごしでしょうか。
10月(神無月)
意味・ニュアンス:秋が深まり、空気が澄んでくる季節
例文
- 拝啓 秋冷の候、貴社のますますのご隆盛をお慶び申し上げます。
- 菊花の候、すがすがしい秋をお過ごしのことと拝察いたします。
11月(霜月)
意味・ニュアンス:秋の終わり・冬の気配が感じられる頃
例文
- 拝啓 晩秋の候、皆様におかれましては一段とご活躍のことと存じます。
- 向寒の候、風邪など召されませんようご自愛ください。
参考記事:【1月〜12月対応】月別ビジネス挨拶文の例文と使い分けポイント
時候の挨拶を使うときの注意点
- 季節に合った表現を選ぶ
- 例:真夏に「木枯らしの候」は不自然
- 相手に合わせる
- 企業宛=「ご清栄」
- 個人宛=「ご清祥」「ご健勝」
- 冗長にしない
- メール=1行程度
- 手紙=2行まで
- 災害・異常気象には配慮
- 「猛暑の候」より「暑さ厳しき折、ご自愛ください」など現実に即した言葉を。
まとめ
時候の挨拶は、ただの形式ではなく、相手を思いやる気持ちを込めた「文の顔」となる部分です。
春夏秋冬・月別の例文をストックしておけば、手紙やメールの冒頭で迷うことはありません。
大切なのは季節感と相手への配慮。
本記事の例文を参考にしつつ、場面に応じて適切な一文を選んでみてください。