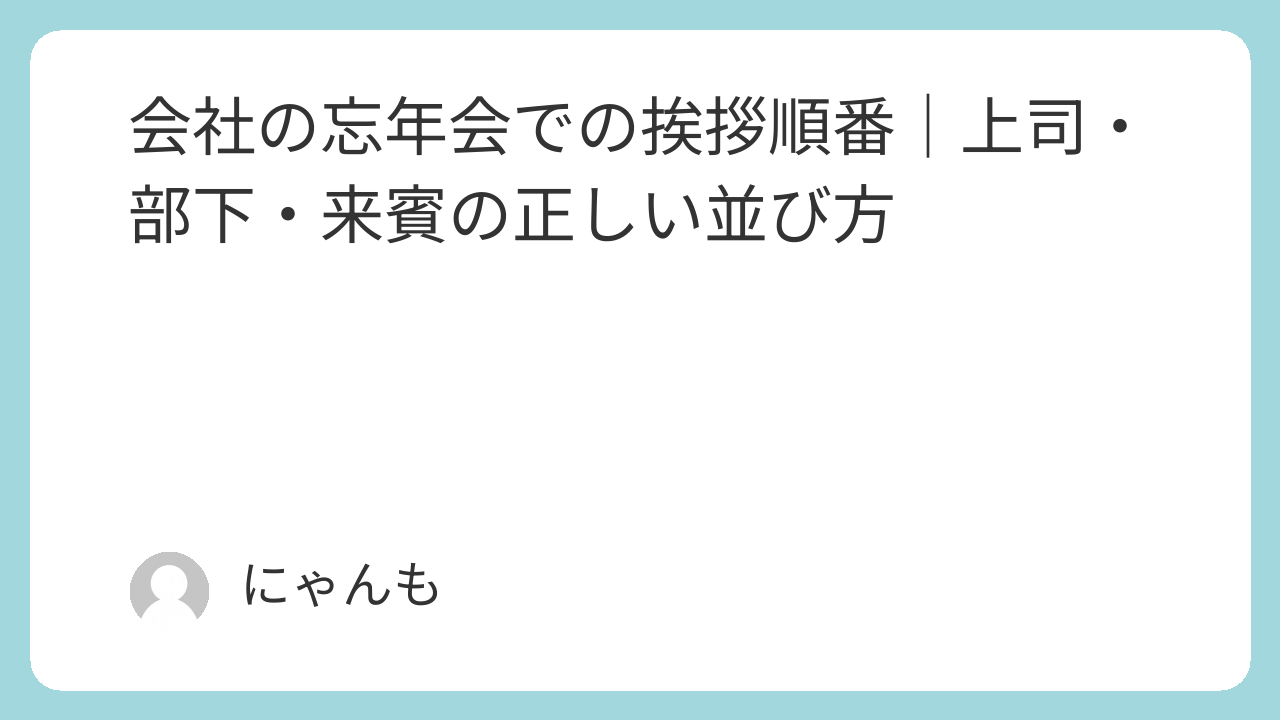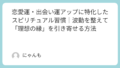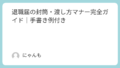会社の忘年会は、1年を締めくくる大切な社内イベントです。
料理や会場も重要ですが、意外と幹事を悩ませるのが「挨拶の順番」。
上司から始めるのか、部下にも発言してもらうのか、来賓がいる場合はどう位置づければいいのか…。
順番を間違えると失礼にあたる可能性もあり、雰囲気を損ねかねません。
そこで本記事では、会社の忘年会における挨拶の正しい順番を解説し、上司・部下・来賓がいる場合の流れや注意点を整理します。
幹事としてスムーズに進行できるポイントを押さえて、参加者全員が気持ちよく締めくくれる忘年会を実現しましょう。
忘年会における挨拶の役割
挨拶は、単なる儀礼ではなく「場を引き締める」役割を持っています。
とくに会社の忘年会では、上司や来賓への敬意を表す意味合いが強く、順番ひとつで組織としてのマナーが問われるのです。
参考記事:忘年会 幹事の挨拶【おもしろ例文集】短くユーモアで盛り上げるコツ
挨拶が果たす3つの役割
- 場の始まりと終わりを整える
開会・乾杯・締めといった節目で雰囲気をつくる。 - 感謝の気持ちを伝える
1年間の労をねぎらい、来賓への配慮も含める。 - 組織の秩序を示す
上司→部下の流れを守ることで、社内の立場関係を円滑に保つ。
挨拶の基本的な流れ
忘年会の進行にはある程度の「型」があります。一般的な流れを把握しておけば、参加者に安心感を与えられます。
標準的な挨拶順
- 開会の挨拶(司会または幹事)
- 「本日はお集まりいただきありがとうございます」から始める。
- 主催者・上位者の挨拶
- 会社であれば社長や役員、部署単位なら部長。
- 来賓の挨拶(いる場合)
- 外部からの参加者がいれば、このタイミングで。
- 乾杯の発声
- 主賓に近い立場の方、または役員が担当。
- 中締め・一本締め(終盤)
- 部長や課長など中間管理職が担当することが多い。
- 閉会の挨拶(幹事)
- 忘年会を締め、二次会への案内などもここで行う。
上司・部下・来賓がいる場合の正しい並び方
上司と部下だけの場合
- 開会挨拶:幹事(部下)
- 挨拶:上司(社長→役員→部長)
- 乾杯:上司(役員や部長クラス)
- 締め:課長や係長など中間層
- 閉会挨拶:幹事
この流れだと、上下関係を守りつつ部下にも役割が回るためバランスが良いです。
来賓がいる場合
- 開会挨拶:幹事
- 主催者挨拶:社長や役員
- 来賓挨拶:招待客
- 乾杯:来賓または上司がお願いする
- 中締め:社内の役職者(部長など)
- 閉会挨拶:幹事
来賓がいるときは、社内序列よりも「外部の方を立てる」意識が大切です。
挨拶を頼むときのマナー
幹事は挨拶を依頼する際も気を遣う必要があります。
依頼のコツ
- 事前に依頼する:当日のサプライズ依頼は失礼。
- 役割を明確に伝える: 「乾杯のご発声をお願いします」など。
- 持ち時間を伝える: 長すぎる挨拶は場を冷めさせるため、目安(1〜2分)を伝える。
挨拶の一言例文
開会の挨拶(幹事)
「皆さま、本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。ただいまより、〇〇部の忘年会を始めさせていただきます。」
上司の挨拶
「本年も皆さんのご尽力により、大変実りある一年となりました。来年も力を合わせて頑張っていきましょう。」
来賓挨拶
「このような場にお招きいただき光栄です。貴社のさらなる発展をお祈り申し上げます。」
乾杯の発声
「それでは、皆さまの健康とご活躍を願い、乾杯!」
中締め
「ここで一度、中締めとさせていただきます。一本締めで締めたいと思いますので、皆さまご唱和ください。」
まとめ
会社の忘年会での挨拶は、単なる形式ではなく「場の雰囲気」を大きく左右します。
- 基本の順番は「幹事 → 上司 → 来賓 → 上位者の乾杯 → 中締め → 幹事の閉会」。
- 来賓がいる場合は、社内序列より来賓を優先。
- 依頼は事前に、持ち時間も伝えるのがマナー。
この流れを押さえておけば、幹事として安心して進行でき、参加者全員が気持ちよく年を締めくくれるでしょう。
おすすめの関連記事
- 忘年会 幹事の挨拶【おもしろ例文集】短くユーモアで盛り上げるコツ
- 忘年会 幹事の役割|社長出席時にふさわしい挨拶例
- 幹事必見!忘年会の乾杯前に使える挨拶フレーズ集
- 忘年会 幹事の締め挨拶|使える例文・NGワード・便利フレーズ集
- 【社内向け】忘年会案内メールの書き方完全ガイド|基本構成・例文・マナーまとめ