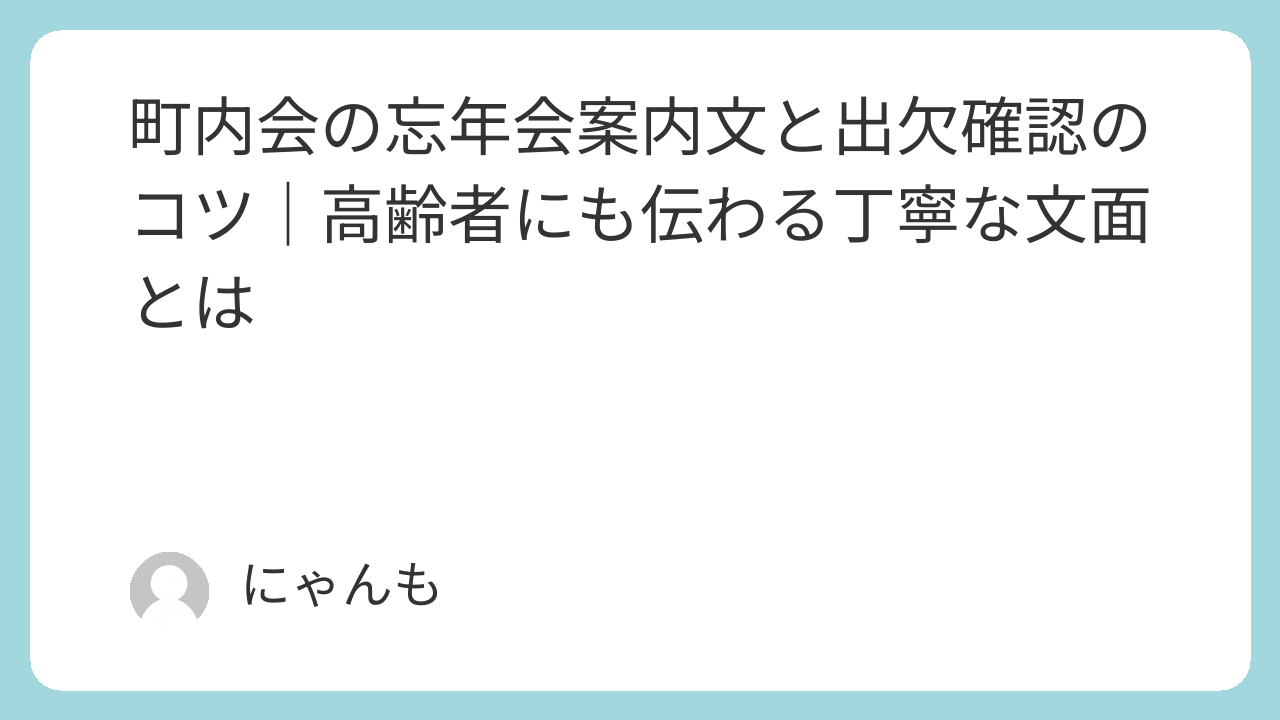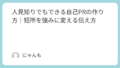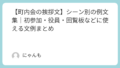町内会の忘年会は、一年を締めくくる大切な行事です。
地域のつながりを深め、日頃の感謝を伝える貴重な場でもあります。
しかし幹事を任されると
「どんな案内文を書けば失礼がないか」
「高齢の方にもわかりやすく伝えるにはどうすればいいか」
と悩む方も多いのではないでしょうか。
特に町内会では幅広い年代が参加するため、ビジネス文のように堅すぎず、かといってフランクすぎないバランスが求められます。
本記事では、町内会の忘年会案内文の作成ポイントや、出欠確認をスムーズに行うコツ、さらに高齢者にも伝わりやすい丁寧な文面例を紹介します。
町内会の忘年会案内文に盛り込むべき基本要素
忘年会の案内文は、読み手がすぐに理解できる「わかりやすさ」が大切です。
特に高齢の方には、複雑な表現よりもシンプルで明確な文章が適しています。
必ず記載すべき内容
- 挨拶と開催の目的
- 「一年間お世話になりました」という感謝の言葉を添える。
- 「親睦を深める会です」と趣旨を一文で明記。
- 開催日時
- 年・月・日・曜日・開始時刻を明確に。
- 例:「令和5年12月15日(金)午後6時より」
- 会場情報
- 会場名・住所・電話番号を記載。
- 必要に応じて地図や案内図を添付すると親切。
- 会費
- 金額と支払い方法(当日集金など)。
- 出欠確認方法と期限
- 「○月○日までに出欠をお知らせください」と明確に。
- 電話・FAX・返信用ハガキなど高齢者にも対応しやすい手段を用意。
- 締めの言葉
- 「皆さまのご参加を心よりお待ちしております」など。
高齢者にも伝わる文面の工夫
町内会の案内は、年齢層を問わず誰でも理解できる表現を意識しましょう。
文面作成のポイント
- 難しい漢字は避ける
例:「御芳志」より「ご寄付」、「御臨席」より「ご出席」の方がわかりやすい。 - 句読点をしっかり入れる
長い一文にせず、読みやすく区切る。 - 敬語は丁寧に、しかしシンプルに
「いただければ幸いです」など、柔らかい敬語を使う。 - 文字サイズに配慮(印刷時)
案内状は大きめの文字で作成すると高齢者にも親切。
出欠確認をスムーズにするコツ
出欠の取りまとめは幹事にとって大仕事です。高齢者や忙しい人でも回答しやすい工夫が必要です。
方法1:返信用ハガキ
- 往復ハガキを利用すれば、切手不要で返信しやすい。
- 「ご出席」「ご欠席」に丸をつけるだけの形式にするとわかりやすい。
返信ハガキの例文
【ご出欠の確認】
□ 出席いたします
□ 欠席いたします
お名前:_________
※該当する方に○をつけてください。
※ご記入のうえ、○月○日までにご投函ください。
方法2:電話・FAX
- 高齢者には電話連絡が確実。
- FAXを活用する地域もあるため、案内文に番号を明記するとよい。
電話での確認例文(幹事側)
「○○町内会の□□です。いつもお世話になっております。12月15日の忘年会について、参加のご予定を伺いたくお電話しました。当日はご都合いかがでしょうか?」
→ 返事をいただいたら「ありがとうございます。当日お待ちしています」「承知しました。また次の機会にぜひご参加ください」とフォローするのが好印象。
方法3:若い世代にはデジタルも併用
- LINEやメールフォームも有効。
- ただし町内会では「紙+電話」を基本にし、デジタルは補助的に使うのが安心。
町内会忘年会案内文の例文
丁寧な案内文(高齢者向け)
町内会の皆さまへ
今年も残すところあとわずかとなりました。日頃より町内会活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。
このたび、ささやかではございますが、忘年会を下記の通り開催いたします。
一年間の労をねぎらい、皆さまと楽しいひとときを過ごしたいと存じます。
記
日時:令和5年12月15日(金)午後6時より
場所:○○会館(△△町1-2-3 電話:000-000-0000)
会費:お一人 3,000円(当日集金いたします)
つきましては、ご出欠を12月5日(火)までに、同封の返信ハガキまたは町内会役員までお知らせください。
皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。
令和5年11月吉日
○○町内会 会長 □□□
カジュアル寄りの案内文(若い世代にも)
町内会の皆さんへ
今年も1年お疲れさまでした!恒例の忘年会を開催します。
ご家族やお友達もお気軽にご参加ください。
日時:12月22日(金)午後6時~
場所:△△会館(駅前すぐ)
会費:大人3,000円 小学生以下1,000円
出欠は12月10日(日)までに、返信ハガキ・電話・LINEのいずれかでご連絡ください。
楽しい会になりますように、たくさんのご参加をお待ちしています!
二次会や送迎に関する案内の工夫
二次会の案内方法
- 忘年会後に二次会を予定する場合は、必ず事前に案内文に記載しましょう。
- 例:「一次会終了後、ご希望の方は近くの△△居酒屋にて二次会を予定しております(会費別途2,000円程度)。」
- 二次会は参加自由であることを強調し、強制参加の雰囲気にならないように注意します。
送迎バスや乗り合いの案内
- 高齢者が多い町内会では、会場までのアクセス配慮が重要。
- マイクロバスを手配する場合は、乗車場所・時間を明記。
- 「車を出せる方に協力をお願いしたい」と案内文に一文添えても良いでしょう。
会費徴収の注意点
会費に関するトラブルを避けるためには、案内文や当日の運営で以下の点に注意しましょう。
- 事前に金額を明記
- 「当日集金」「事前徴収」を明確にする。
- お釣りを用意
- 3,000円や5,000円など、千円単位に設定すると便利。
- 集金係を決める
- 幹事だけでなく役員のサポートを得るとスムーズ。
- 高齢者には個別対応
- 「当日持参が難しい場合は役員までご相談ください」と案内に添えると安心感を与えられる。
忘年会当日の進行例
案内文や出欠確認だけでなく、当日の進行も幹事の腕の見せどころです。段取りがしっかりしていると参加者が安心し、会がスムーズに進みます。ここでは標準的な流れを紹介します。
1. 開会の挨拶(司会・幹事)
- 開始時刻になったら司会役(幹事)が前に立ち、会をスタート。
- 簡単な挨拶例:
「皆さま、本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。ただいまより、○○町内会の忘年会を始めさせていただきます。」
2. 主催者挨拶(町内会長や役員)
- 忘年会の趣旨や一年間の労をねぎらう言葉を述べてもらう。
- 例文:
「本年も町内会活動に多大なるご協力をいただき、誠にありがとうございました。来年も皆さまとともに地域を盛り上げていきたいと思います。」
3. 乾杯の発声
- 会長、または年長の方にお願いするのが一般的。
- 例文:
「それでは皆さま、今年一年の健康と町内のますますの発展を祈念して、乾杯!」
4. 会食・歓談
- 司会は進行を過度に仕切らず、自由に食事と歓談を楽しんでもらう。
- 余興やビンゴ大会を予定している場合は、事前にプログラムを簡単に伝える。
5. 中締め(一旦の締め)
- 忘年会の終盤に差しかかったら「中締め」を行い、二次会に移行する人と帰宅する人を区切る。
- 中締めは副会長や役員にお願いするのがベター。
- 一本締め・三本締めが定番。
- 例文:
「ここで一度、中締めとさせていただきます。今年一年、皆さま本当にお疲れさまでした。では、皆さまご唱和をお願いします。」
6. 閉会の挨拶(幹事)
- 最後に幹事が感謝の言葉と、二次会や今後の予定を伝える。
- 例文:
「本日はご参加いただきありがとうございました。来年も町内会活動にご協力をお願いいたします。本日はこれにてお開きといたします。お気をつけてお帰りください。」
忘年会で使える挨拶文例集
実際にマイクを持つと「何を言えばいいか分からない」と戸惑う方も多いもの。ここでは、開会・乾杯・中締め・閉会の場面で使える挨拶文例を複数紹介します。状況に応じてアレンジしてください。
1. 開会の挨拶(幹事・司会)
フォーマルな例
「皆さま、本日はご多忙の中お集まりいただき、誠にありがとうございます。これより○○町内会の忘年会を始めさせていただきます。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。」
カジュアルな例
「こんばんは!本日は忘年会にご参加いただきありがとうございます。今年も町内会の活動を通して皆さんとつながりを感じられたことに感謝しています。それでは、楽しい時間を過ごしましょう!」
2. 乾杯の挨拶(会長・年長者)
定番の例
「本年も皆さまのご協力のおかげで、無事に町内活動を進めることができました。来年も健康と幸せに満ちた一年となりますよう祈念いたしまして、乾杯!」
短めでシンプルな例
「皆さまの健康と町内会のさらなる発展を願って、乾杯!」
3. 中締めの挨拶(副会長・役員)
一本締めを伴う例
「本日はご参加いただきありがとうございました。今年一年、町内会を支えてくださった皆さまに心から感謝申し上げます。それでは、これからの一年も実りあるものとなりますよう、一本締めで締めたいと思います。よろしくお願いします。」
三本締めを伴う例
「おかげさまで楽しい忘年会となりました。皆さまのご健康とご多幸を祈りまして、ここで三本締めをさせていただきます。よーっ!」
4. 閉会の挨拶(幹事)
丁寧な例
「皆さま、本日はお忙しい中ご参加いただき、誠にありがとうございました。来年も町内会活動にご協力を賜りますようお願い申し上げます。お気をつけてお帰りください。」
二次会案内を添える例
「本日の一次会はこれでお開きといたします。なお、ご都合のつく方は近くの△△で二次会を予定しておりますので、ぜひご参加ください。それでは、来年もどうぞよろしくお願いいたします。」
ビンゴ大会や余興のアイデア集
忘年会を盛り上げるには、食事や歓談だけでなく「みんなで楽しめる余興」があるとより一層思い出に残ります。町内会の特色を活かしつつ、世代を問わず楽しめる企画を選ぶのがポイントです。
1. ビンゴ大会
- 定番ながら盛り上がりやすく、ルールもシンプルで高齢者にも理解しやすい。
- 景品は「日用品」が人気。例:タオルセット、洗剤、調味料、お米など。
- 小さなお子さんにはお菓子セットを用意すると喜ばれる。
2. くじ引き大会
- 会費の一部を景品代に充てて抽選会を実施。
- 番号付きのカードを配布し、司会が番号を読み上げるスタイル。
3. カラオケ大会
- 音響機材があれば、カラオケは世代を超えて盛り上がる定番余興。
- 順番を決めず「歌いたい人どうぞ」とすると気軽に参加できる。
- 歌が苦手な人にも配慮して、参加自由であることを強調。
4. クイズ大会
- 「町内会クイズ」「昭和の懐かし歌クイズ」などテーマを絞ると盛り上がる。
- チーム対抗にすると世代交流が自然に生まれる。
5. 子ども向け企画
- お菓子のつかみ取り
- 風船割りゲーム
- 簡単な工作コーナー
家族参加型の町内会では、子どもたちの出番をつくると保護者も安心して楽しめる。
6. 伝統芸・特技披露
- お囃子や民謡、太鼓など地域に根付いた芸能を取り入れるのもおすすめ。
- 「町内の有志によるマジックショー」など手作りの余興も雰囲気が和む。
案内を送るタイミングとマナー
- 1か月前の送付が理想:高齢者は予定を早めに立てるため、十分な余裕をもたせる。
- 再度の案内(リマインド):期限が近づいたら電話や回覧でフォロー。
- 案内後の配慮:体調や事情で直前に欠席する方も多いので「無理のない範囲で」と一文添えると安心感を与える。
幹事のためのチェックリスト|準備から後片付けまで
忘年会を成功させるためには、段取りと準備が何より大切です。以下のチェックリストを参考にすれば、抜け漏れなくスムーズに運営できます。
【1か月前まで】準備段階
☑ 会場を予約(人数・アクセス・送迎の有無を確認)
☑ 予算を決定(会費・町内会費補助・景品代など)
☑ 案内文を作成・印刷
☑ 出欠確認方法を決定(返信ハガキ・電話・LINEなど)
☑ 役割分担を決定(司会、会費集金、受付、余興担当など)
【2~3週間前】案内と調整
☑ 案内文を配布・回覧・郵送
☑ 出欠確認の回収状況を確認
☑ 高齢者や不在の家庭へ個別電話で確認
☑ 余興・景品を準備(予算内で購入・寄付のお願いも可)
【1週間前】最終確認
☑ 出欠を確定し、会場へ人数を連絡
☑ 座席表やプログラムを作成(高齢者には移動しやすい席を配慮)
☑ 会費徴収方法を確認(当日集金なら釣り銭を用意)
☑ 送迎バスや乗り合わせを調整
☑ 必要な備品(マイク・ビンゴカード・筆記用具・テープ類など)を揃える
【当日】忘年会運営
☑ 受付を設置(会費徴収・名簿チェック)
☑ 開会の挨拶 → 会長挨拶 → 乾杯 → 会食 → 余興 → 中締め → 閉会
☑ 写真撮影(町内会の記録や広報誌用に)
☑ 高齢者や子どもへのフォロー(食事の配膳や送迎)
☑ 二次会に参加する人へ案内
【翌日以降】後片付け・報告
☑ 会場費・飲食代を精算
☑ 会計報告を町内会に提出
☑ 景品や備品の在庫を確認・保管
☑ 参加者へお礼の言葉を回覧や掲示板で共有
☑ 写真や報告を次回の回覧板や会報に掲載
よくある質問(FAQ)
Q1. 忘年会の案内文は何日前に送ればいいですか?
A. 少なくとも 1か月前 に配布するのが理想です。高齢者は予定を早めに立てる傾向があるため、余裕を持った案内が喜ばれます。遅くとも2週間前までには案内しましょう。
Q2. 出欠確認の返信が集まらないときはどうしたらいい?
A. 期限の1週間前になっても返信がない場合は、電話での確認が効果的です。高齢者世帯ではハガキやLINEより電話の方が確実に返答を得られます。
Q3. 欠席の連絡が直前にあった場合、会費はどうする?
A. 基本的には「参加者のみ徴収」とするのが町内会の慣例です。ただしキャンセル料が発生する会場の場合は、案内文に「直前の欠席は会費をいただく場合があります」と記載しておくとトラブル防止になります。
Q4. 町内会の忘年会に子どもも参加できますか?
A. 多くの町内会では「家族参加OK」です。案内文に「ご家族もご一緒にどうぞ」と一文を添えると、子育て世代も参加しやすくなります。子ども料金を設定すると公平です。
Q5. 送迎を手配する必要はありますか?
A. 会場が遠い場合や高齢者の参加が多い場合は、送迎を用意すると喜ばれます。マイクロバスをレンタルするか、車を出せる方に協力をお願いするのが現実的です。
Q6. 景品や余興は必ず必要ですか?
A. 必須ではありませんが、あると盛り上がります。特にビンゴ大会や抽選会は定番で、世代を問わず楽しめるためおすすめです。予算に余裕があれば取り入れましょう。
Q7. 会費はいくらくらいが妥当?
A. 一般的には 2,000〜4,000円程度 が相場です。高齢者世帯や子ども連れ家庭にも配慮して、低めの設定にする町内会も多いです。町内会費からの補助がある場合は、案内文で明記すると安心です。
まとめ
町内会の忘年会案内文は、わかりやすく、丁寧に、相手の負担を減らすことが大切です。
- 基本情報(日時・場所・会費・出欠方法)を明記。
- 高齢者には大きめ文字とシンプル敬語で。
- 出欠確認は「返信ハガキ+電話」を基本にし、若い世代にはデジタルも併用。
- 二次会や送迎の情報を添えれば参加しやすさが増す。
- 会費徴収は事前に方法を明確にし、当日の混乱を防ぐ。
- 当日の進行は「開会 → 会長挨拶 → 乾杯 → 会食 → 中締め → 閉会」が基本。
- 挨拶は定型文を準備しておけば安心。
- 余興(ビンゴ、クイズ、カラオケなど)で盛り上げる工夫を。
- チェックリストで準備から後片付けまで管理すれば、幹事業務が格段に楽になる。
- FAQを事前に共有しておくと、参加者の不安も解消できる。
町内会の忘年会は、単なる宴会ではなく「地域のつながりを深める大切な場」です。
幹事の心配りと丁寧な準備が、参加者全員にとって忘れられない温かい時間をつくるでしょう。
👉 おすすめ記事: