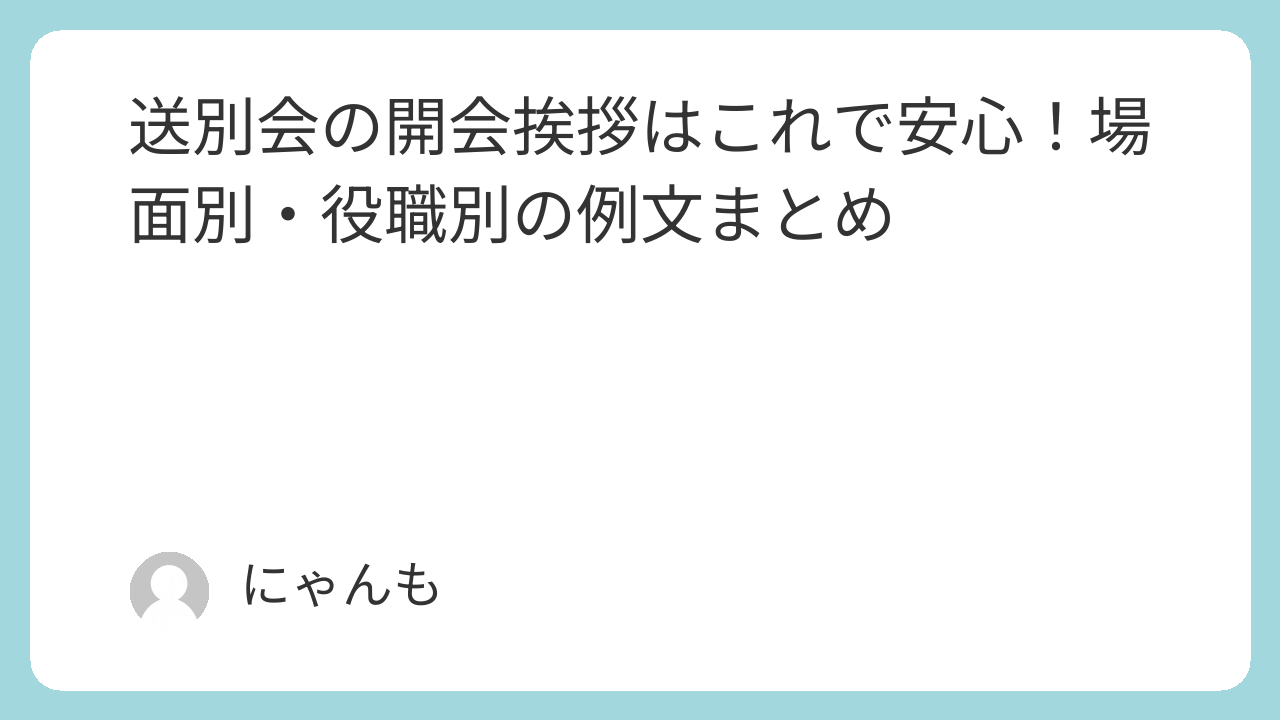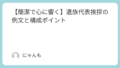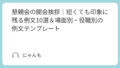送別会で開会の挨拶を任されると、「何を話せばいいのだろう」「失礼にならないか」と緊張する方も多いでしょう。
特に職場や学校、地域の送別会では、立場や役職に合わせた言葉選びが重要です。
この記事では、送別会の開会挨拶の基本ポイントから、シーン別・役職別にすぐ使える例文までをまとめました。
これを読めば、当日の挨拶も安心して臨むことができます。
送別会の開会挨拶の基本構成
送別会の開会挨拶には、一定の流れがあります。まずは基本の構成を押さえておきましょう。
- 挨拶と自己紹介
- 「ただいまご紹介にあずかりました〇〇です」
- 「本日はお集まりいただきありがとうございます」
- 送別会の趣旨を伝える
- 「本日は〇〇さんのご退職を祝し、これまでのご功績を讃える会です」
- 参加者への感謝
- 「ご多用の中お集まりいただき、心より感謝申し上げます」
- 送られる人への一言
- 「〇〇さんには長年にわたり多大なご尽力をいただきました」
- 会のスタートを宣言
- 「それでは、送別会を始めさせていただきます」
この流れを意識すれば、大きな失敗は避けられます。
場面別の送別会開会挨拶の例文
職場(会社・部署)の場合
送別会の多くは職場で行われます。上司・同僚・後輩と立場が入り混じるため、全員に配慮した言葉選びが求められます。
例文:
「皆さま、本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日の送別会は、長年にわたり当部署を支えてくださった〇〇課長のご功績を讃えるとともに、新たな門出をお祝いする場です。〇〇課長には多大なご指導をいただき、私たちも多くを学ばせていただきました。どうぞ本日は、感謝の気持ちを込めて、楽しいひとときをお過ごしください。それでは送別会を始めさせていただきます。」
学校・サークルの送別会
卒業や引退に伴う送別会では、感謝と未来への応援の言葉を中心に。
例文:
「本日は、私たちの先輩である〇〇さんをお送りするために、このように多くの方にお集まりいただきました。〇〇さんは、いつも私たちを導き、支えてくださった存在です。先輩の新たな挑戦を、心から応援しております。本日は感謝を込めて、皆で楽しい時間を過ごしてまいりましょう。」
家族や地域での送別会
アットホームな場では、形式ばらず温かみのある挨拶が好まれます。
例文:
「今日は〇〇さんの新しい旅立ちを祝うために、家族・友人・ご近所の皆さんに集まっていただきました。これまで地域や私たちにたくさんの思い出を残してくださり、本当にありがとうございます。新天地でもご活躍されることを祈りつつ、本日は楽しい会にしてまいりましょう。」
役職別の開会挨拶の例文
上司としての挨拶
「本日は、〇〇さんの長年のご尽力を讃えるべく、これだけ多くの方にお集まりいただきました。部下を指導する立場から見ても、〇〇さんの姿勢には学ぶことが多くありました。今後の新たな環境でもご活躍されることを心より願っております。」
同僚としての挨拶
「本日は、共に働いた仲間である〇〇さんの門出を祝うために、多くの方にお集まりいただきました。〇〇さんの明るさや気配りは、私たちにとって大きな支えでした。これからのご活躍を応援しつつ、今日は楽しい時間を過ごしましょう。」
後輩としての挨拶
「本日は、私たちに多くのことを教えてくださった〇〇先輩をお送りするために集まりました。先輩のご指導は、今後も私たちの糧になります。これからの新たな挑戦が素晴らしいものになることを祈りつつ、本日は皆さんと一緒にお祝いさせていただきたいと思います。」
開会挨拶を成功させるポイント
- 長すぎない
→ 1〜2分程度が目安。簡潔さが大切です。 - 笑顔を意識する
→ 硬い雰囲気ではなく、温かさを出すと場が和みます。 - 相手に敬意を払う
→ 送られる人の功績や人柄を盛り込むと気持ちが伝わります。 - 場に合ったトーンで
→ フォーマルな場では丁寧に、仲間内では柔らかく。
NG例から学ぶ!送別会の開会挨拶で避けたいポイント
送別会の開会挨拶はシンプルで良いのですが、意外とやってしまいがちな「失敗パターン」もあります。以下はNG例とその理由です。
1. 長すぎる挨拶
「本日は〇〇さんの…えーと…あの…」とダラダラ続くと、聞いている人が退屈してしまいます。1〜2分程度で簡潔にまとめましょう。
2. 内輪ネタばかり
「この前の飲み会で〇〇さんが泥酔して…」といった一部しか分からない話は、場の雰囲気を壊すことも。内輪ネタは控えめに、誰もが共感できる内容を選ぶのが無難です。
3. ネガティブ発言
「いなくなって寂しい」「戦力が減って困る」などの発言は場を暗くします。感謝や期待を込めた前向きな言葉を選びましょう。
4. 自分語り
「実は私も昔…」と自分の話に寄せすぎるのも避けたいポイント。送別会の主役は「送られる人」であることを忘れずに。
ユーモアを交えた送別会の開会挨拶例文
送別会の雰囲気によっては、少しユーモアを交えることで場が和みます。ただし、相手や場に応じてバランスをとることが大切です。
軽いユーモアを交える例(職場向け)
「本日は〇〇さんの送別会にようこそお集まりいただきました。〇〇さんといえば、我が部署の“最終兵器”でしたが、本日をもちましてその兵器は他の場所に移籍してしまいます…。私たちは正直、戦力ダウンで不安もありますが、それ以上に〇〇さんの新天地での活躍が楽しみです。本日は笑顔でお見送りできるよう、皆で盛り上げていきましょう!」
親しい仲間内でのユーモア例
「本日は〇〇さんの送別会ですが、正直まだ実感が湧きません。明日も普通に会社に来そうですよね?(笑)でも、もう来週からは違う場所で新しい挑戦が始まります。寂しさはありますが、今日はその門出を楽しくお祝いしましょう!」
家族・地域向けのユーモア例
「今日は〇〇さんをお送りする会ですが、もうすでに『次に帰ってくるのはいつ?』という話題で盛り上がっております(笑)。それだけ〇〇さんが愛されている証拠ですね。本日は笑顔で新たな門出をお祝いしましょう!」
送別会で使える「乾杯の挨拶」例文
送別会で開会の挨拶が終わると、次に多くの場合「乾杯の挨拶」が続きます。こちらも簡潔で、場を盛り上げるのがポイントです。
基本構成
- 一言挨拶(例:「ただいまご紹介にあずかりました〇〇です」)
- 送られる人への感謝とねぎらい
- 今後の活躍を祈る言葉
- 乾杯の発声
例文(フォーマルな場面)
「それでは僭越ながら乾杯の音頭を取らせていただきます。〇〇さんには長年にわたり多大なご貢献をいただきました。新天地でもますますのご活躍を心よりお祈りいたします。本日は感謝を込めて、皆で楽しい時間を過ごしましょう。それではご唱和をお願いいたします。〇〇さんのご健勝と今後のご活躍を祈念いたしまして――乾杯!」
例文(カジュアルな場面)
「それでは皆さん、グラスのご用意をお願いします!本日、私たちの大切な仲間である〇〇さんをお送りするにあたり、感謝と応援の気持ちを込めて乾杯したいと思います。〇〇さんの新しい門出に幸多からんことを祈って――乾杯!」
送別会の「閉会の挨拶」例文
送別会の最後を締める「閉会の挨拶」は、感謝を述べつつ参加者全員が気持ちよく会を終えられるようにする役割があります。
基本構成
- 本日の会への感謝
- 送られる人へのねぎらいと今後へのエール
- 参加者への謝辞
- 閉会の言葉
例文(上司・幹事向け)
「本日はご多用の中、〇〇さんの送別会にご参加いただきありがとうございました。〇〇さんのこれまでのご功績に、改めて深く感謝申し上げます。新たな環境でもますますのご活躍をお祈りいたします。どうぞ皆さま、本日の思い出を胸に、引き続きご交流いただければ幸いです。これをもちまして送別会をお開きとさせていただきます。」
例文(カジュアルな場面)
「本日は、〇〇さんを囲んで楽しい時間を過ごすことができました。〇〇さんのこれからの道が素晴らしいものになりますよう、心から応援しております。最後に改めて感謝の気持ちを込めて、今日の会を締めたいと思います。本日はありがとうございました!」
開会から閉会までの流れをイメージしよう
送別会のスピーチは、開会 → 乾杯 → 中盤のスピーチや余興 → 閉会 という流れが一般的です。それぞれの役割を理解して準備すれば、安心して本番を迎えられます。
- 開会挨拶:会の趣旨を伝え、場を和ませる
- 乾杯挨拶:場を盛り上げ、会をスタートさせる
- 閉会挨拶:感謝を伝え、余韻を残して締める
これらをバランスよくこなせば、送別会全体がスムーズで温かい雰囲気になります。
送別会でよくある質問(FAQ)
Q1. 開会挨拶はどれくらいの長さがベストですか?
A. 目安は 1〜2分程度 です。長すぎると会のスタートが重くなるため、簡潔にまとめましょう。
Q2. 挨拶の順番は誰が担当するべき?
A. 一般的には以下の流れになります。
- 開会挨拶:主催者や幹事、または上司
- 乾杯の挨拶:役職が高い人や、主役と関わりの深い人
- 閉会挨拶:再び主催者や幹事
ただし、会社や団体の慣習によって違う場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
Q3. ユーモアはどこまで入れていいですか?
A. 場の雰囲気によります。フォーマルな場では控えめに、親しい仲間内では多少砕けた話題も歓迎されます。ただし 相手をからかいすぎない ことが重要です。
Q4. 原稿を読んでも大丈夫?
A. 問題ありません。特に緊張する方はメモを持っていても自然です。大事なのは、顔を上げて笑顔で話す ことです。
Q5. 最後に「三本締め」や「一本締め」をするのはアリ?
A. 職場や地域によってはよく行われます。閉会挨拶のあとに「最後に一本締めで締めたいと思います」と入れると、メリハリのある終わり方になります。
Q6. 送別会で注意すべきマナーは?
A. 以下の点に気をつけましょう。
- ネガティブな話題は避ける
- お酒の強要をしない
- 主役が一番楽しめる雰囲気をつくる
これを守るだけで、送別会は温かく心地よい場になります。
最終まとめ
送別会の挨拶は「開会」「乾杯」「閉会」とそれぞれに役割があります。
- 開会挨拶:会の雰囲気をつくり、趣旨を伝える
- 乾杯の挨拶:場を盛り上げ、スタートを切る
- 閉会の挨拶:感謝と応援を伝え、気持ちよく締める
また、NG例を避け、適度にユーモアを交えることで、より印象的で心のこもったスピーチになります。今回紹介した例文を参考に、送別会を成功へと導いてください。